
・・・
「あなたはそろそろ“終わり”になりますね。」
玄関を開けると、そこに立っていた彼女がそう言った。
彼女とは面識がなかったが、きっとそういう役割なのだろう。
「そうなんですか。“終わり”はいつ頃なのですか?」
「はっきりとは言えませんが、もうすぐです。」
「そうですか。もう少し早かったら丁度良かったんですけどね。そうだなぁ、昨年の春頃なら一番よかったかな。」
彼女は、僕が残念そうな顔をしているのが気になったのだろう。
「ご希望に沿えず申し訳ありませんが、決まっていることですので。」
そう言って、視線を落とした。
「いえ、いいんですよ。まぁ、今でも悪くはないし。それに・・・」
「それに?」
「それにあなたのせいじゃない。」
彼女のせいなのかどうかは分からなかったけど、気にさせるのが悪かったのでついそう言ってしまった。
「では、いろいろとご用事もおありでしょうから、私はこれで失礼いたします。」
彼女は視線を上げて僕を見ると、そう言って帰っていった。
・・・
僕はドアを閉めて、部屋に戻り、コーヒーを1杯分落としてカップに移した。
原稿の締切が終ったところだったし、取り立ててしておかないといけないことは思い浮かばなかった。とりあえず、クライアントにしばらく仕事が請けられなくなることをメールに書いて送った。
コーヒーを飲み終わってしまうと、僕はやることがなくなってしまった。
日頃の癖でシャワーをして、ベランダに出た。
夜空を眺めていると、どうしても最後に話をしたくなったので電話をかけた。
呼び出し音はとても長いように感じたし、受話器から聞こえる声はとても平板な気がしたけど、気のせいかもしれない。
「そろそろ僕は終わりなんだそうだよ。」
「そうなんだ。残念だね。」
「君が悲しんでくれるうちに終わりになれば良かったんだけどなぁ。」
「でも、それはあなたが選んだことだから仕方ないわ。」
「そうだね、君の言うとおりだ。」
もうそれ以上何も言うことがなかった。
「それじゃあ、さようなら。」
「うん、さようなら。」
簡単なお別れの挨拶をして僕らは電話を切った。
特に理由はなかったが、電話に保存されている住所録と発着信履歴とメールをすべて消した。もう電話を使うこともないだろう。
そうしてしまうと、とても身軽になった気がした。
僕は部屋に入り、メモパッドから用紙を 1 枚、丁寧に切り取った。
いつも使っている“馴染み”のボールペンのインクがちゃんと出るのを確認するために、雑誌の裏にぐるぐると丸を描いた。
そして、僕はこれまで書いたどの文字より丁寧にメモ用紙に書いた。
「ありがとう」
メモに最初に気付いてくれた人へのメッセージになればいいな、と思いながら、テレビの前のいつも使っている小さなテーブルの上にメモを置いて、メモが飛ばないようにラナンキュラスの一輪挿しをメモの隅に置いた。
僕は部屋の明かりを消して、横になった。
遠くの方で誰かが「Blackbird」を口ずさんでいるのが聴こえたような気がした。
・・・
※ このブログは「土曜日、公園にて」に掲載した“お話”を修正・加筆したものです。最新の“お話”は「土曜日、公園にて」に不定期で掲載しています。











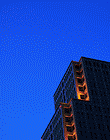
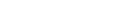 まで
まで