【連載】 新月前夜、窓、そして君の事。
※ この小説は、2009年12月21日から2010年3月4日まで、「土曜日、公園にて」で連載したものですが、まとめて読めるようにしてほしいというご要望があり、ここに載せることにしました。この小説には多くのコメントとメールをいただきましたが、それらは元の連載をご覧いただければと思います。また、第2話以降は「続きをよむ」からお読みいただけます。では、お楽しみください。※
***
*** 第1話: 「窓」
***

文・イラスト: セキヒロタカ
あれは何年前の冬だったかな。 骨のように白く細くなった月が新月になる前の晩だった。僕が「そのこと」に気づいたのは。
その日はとても晴れていて、放射冷却で外は冷え込んでいたのだけど、ブラインドの隙間から見えた三日月が気になり、ふとベランダに出たくなった。
原稿締め切りの直前だった僕は、風邪を引いてしまわないように、ファーがたっぷり付いたランチコートを着込んだ。そして、お湯を沸かして温かいコーヒーを作り、蓋付きのマグカップに入れて、ベランダに出た。
コーヒーを飲みながらベランダで月を眺めていると、僕の部屋から見て月の端がビルにかかったとき、そのビルの最上階の部屋の明かりが点いて消えてを2度繰り返した。
僕はなぜかそれが妙に気になったが、そんなことはひと月も経たないうちに忘れていた。
その翌月、その日が新月の前の晩だったことを思い出し、先月妙に気になっていたことを一緒に思い出した。
僕がベランダに出て新月前の三日月を観察していると、月の端がビルにかかったとき、またあのビルの最上階の部屋の電気が2度点滅した。
僕はそれ以来、とてもそれが気になり、毎月、新月の前の晩になると、三日月とそのビルの最上階の部屋の電気を観察した。
・・・
そう。
その新月の前の晩も同じように僕はその部屋(正確に言うと、そこに明かりがつくであろう窓のような場所)と三日月を観察していた。
しかし、それはいつもの新月の前の晩とは違った夜になった。
【この続きは↓「続きを読む」をクリック。】
***
*** 第2話: 「緑の光」
***
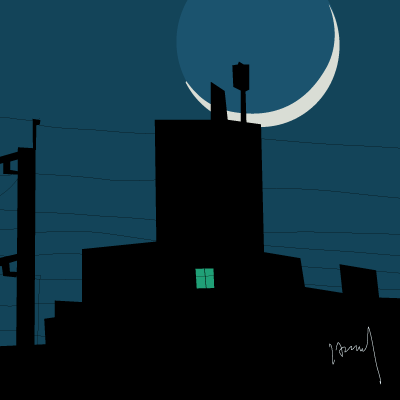
文・イラスト: セキヒロタカ
その夜もとても寒い冬晴れの日の夜だった。
僕は、細くて白い三日月がビルに近づいてきたことを確認してから、いつものように淹れたてのコーヒーを蓋付きのマグカップに入れ、フード付きのダウンジャケットを着込んでベランダに出た。
初めて「このこと」に気付いた日もこんな寒い日だったな、と思った。
僕は、それが何年前のことだったか僕は思い出そうとしたけど、なぜかどうしても思い出せなかった。
ふと気づくと、もう三日月の端がビルに隠れる寸前だった。
僕はその一瞬を見逃さないように目を凝らしていた。
部屋の明かりが点いた。
いつもと違ったのは、それからだった。
その日は、その明かりは点いたまま消えなかった。
今でも不思議なのだけど、そのとき僕が奇妙に思ったのは、明かりが点いたままになっていることより明かりの色だった。
「今日は緑だ。」
いつもと違う、鮮やかな緑色だった。
じゃあ、いつもは何色だったか、と訊かれると、まったく思い出せない。
モノクロームの夢の中に赤い夕日が現れたとたん、それまでそこに色がなかったことに気付く、そんな感じだ。
そしてその緑の明かりはずっと点いたままだった。
緑の歩行者信号のようだった。
「もう待っていなくていいんだ。行っていいんだ。」
と言っているように思えた。
僕は何か起こりそうな気がしてずっと見ていたのだけど、コーヒーも底をつき、体も冷えてきた。
「きっと、カーテンの色を変えたとか、それだけのことだよ。」
僕はそう思うことにして、部屋に入った。
そして、バスタブに湯を溜めて体を温めてからベッドに入った。
僕はベッドの中でうとうとしながら、明日「あの」ビルに行ってみようと考えていた。
***
*** 第3話: 「そのビルへ」
***

文・イラスト: セキヒロタカ
次の日、僕はどうしてもあの明かりが気になったので、原稿書きに入る前にそのビルの下まで行くことにした。ニットにツイードのダウンベストを羽織り、厚手のニッカホーズを履いて自転車で出かけた。
「そこ」に行くのは初めてだった。
方角はわかるのだけど、距離はほとんどわからない。
街中はまっすぐ走れないのだ、ということに走り出して改めて気付いた。
オフィスビルやコンビニエンスストア、中華料理店などをジグザグにかわしながら、僕は自転車で「その」ビルに向かった。
途中、鉄道の下をくぐる道を通り、自転車用のスロープのある歩道橋を2度越えた。
そして、「そのビル」の下に着いて僕が見たのは、壁面をすっぽり覆われた建物だった。
・・・
そのビルは壁面工事中だったのだ。
昨夜は明かりがはっきり見えたから、きっと今朝工事を始めたんだろう。
ひょっとしたら僕がいつも見ている方向が違うのかも、と思い、ビルをぐるっと回って見てみた。僕の部屋はこの建物から見ると東に位置しているのだけど、東側はすぐ近くに高架の線路が通っているのでよくわからない。
僕は、線路をはさんで斜め向かいにある8階建ての雑居ビルのエレベータで上に上って見てみることにした。
雑居ビルの1階のイタリアのカジュアルファッションを扱う店を通り抜けて、エレベーターホールに行った。消費者金融や歯医者、会計事務所といった中にメガネ店を見つけた。6Fだった。ここなら部外者が簡単に入れそうだ。
僕は6Fまでエレベータで上がった。
メガネ店は雑居ビルの6Fフロアの南半分を占有している結構大きな店舗だった。
僕はメガネのフレームを見るフリをして、「あの」ビルの壁面が見えるところを探し、西の窓のほうに移動した。窓際に陳列してあるメガネフレームと日除けのハーフシェードが邪魔にはなったが、「あの」ビルの壁面が見えた。
東側の壁面も上まで足場が組まれ、厚手のメッシュで覆われていた。
やはり、今朝工事が始まったのだ。
それにしてもすばやい工事だ。
朝始めて、もう足場が組まれ、メッシュで覆われている。もしかしたら、下半分くらいは昨日の時点ですでに足場が組まれていたのかもしれない。
僕の部屋との位置関係や風景から考えて、「あの」窓はメガネ店からは左上に見える部屋の窓のはずだ。メガネ店から見ると「あの」窓が足場とメッシュで覆われていることはわかるものの、足場が邪魔になり、その窓がどうなっているか詳しくはわからない。
「どのようなフレームをお探しですか?」
振り返ると、真新しい白のブラウスとライトグレーのツイルのタイトスカートの女の子が僕の後ろに立っていた。「あの」窓の場所を探すのに夢中で彼女が後ろに来たことに気づいていなかったのだ。
「あ、特に探している、というわけでもないのだけど、近くを通りかかったので。」
意味不明の言い訳だと思いつつそう言うと、彼女は、御用がございましたらまたお呼びください、と静かに言い、笑顔で会釈してカウンターの方に戻っていった。きっと彼女ならとても感じよく朝の天気予報を読めるだろう、という感じの笑顔だ。
僕は、「あの」窓の場所がもっとよく見える場所を他で探すことにして、メガネ店を出ることにした。
「ありがとうございました。」
静かな朝の天気予報の女の子の声を聞きながら僕は店を出てエレベーターに乗った。
僕は雑居ビルを出て、周りのビルで上に上がれそうなところを探してみたが、見当たらなかった。
・・・
僕は、あきらめて自転車で帰ることにしたが、あの窓と明かりのことが気になって仕方がなかった。
***
*** 第4話: 「朝の天気予報の彼女」
***

文・イラスト: セキヒロタカ
僕は、部屋に帰り、仕事の準備をしながら、やはり「あの」部屋と窓のことを考えていた。仕事の準備をし終えると、僕はまたベランダに出て、足場とメッシュで覆われたあのビルを眺めた。
足場では作業員が壁面工事を進めているようだった。
そのとき、何人かの作業員が「あの」窓のところに集まり、何かをし始めたように見えた。そのビルまでは距離があるし厚いメッシュ越しなのではっきり見えない。
僕は必死で目を凝らしたが何をしているかはよくわからなかった。僕はカメラの望遠レンズなら何か見えるかもしれないと思い、急いで部屋に入ってカメラを持ち出し、ファインダー越しに覗いたが、僕の持っている程度の望遠レンズでは肉眼とほとんど変わらなかった。ただ、作業員が何かを運び出しているように見えた。
僕はなんとか見ようとしたがやはりはっきりは見えなかった。
その後、そのビルは不透明なシートで完全に覆われてしまい。
ビルの壁面はまったく見えなくなってしまった。
それから僕は、雨降り以外はほぼ毎日自転車で「その」ビルの下に行った。毎日のロードワークのコースに組み込んだのだ。
壁面の工事なのになかなかシートと足場は撤去されなかった。正面側の工事の内容を示すボードには、工期が 1ヶ月くらいに亘ることが記されていた。
これまでも何度か入居者の名前を見に行こうかとも考えたのだけど、そのビルはオフィスビルというよりマンションのような形態だったので、うろうろして1Fの入り口近くにいる守衛に不審者と思われてしまうことが心配で見に行っていなかった。
ただ、その日は決心して確かめに行くことにした。
そのビルの入り口は東側にある。つまり、僕の部屋に向いているのだけど、間に高架の線路があって、ビルの出入りの状況は僕の部屋からは見えない。
僕は道を挟んだ向かい側の歩道から、そのビルの入り口を覗いてみた。入ってすぐ左手に入居者のプレートが入るボードがあり、右手にステンレス製の集合ポストがあった。運送屋が直接ドアを開けて、その奥にあるエレベーターを使っているので、オートロックではないようだ。
僕は携帯電話で話をしているフリをしながらしばらく様子を伺った。それから道を渡り、「その」ビルのドアを開けた。
1Fはエレベーターホールと守衛室とポストがあるだけで、小さな蛍光灯以外は明かりもなく、外からの光が主たる光源といった感じだった。
僕は、行き先を探しているフリをしながら、最上階の部屋のプレートを探した。法人住民税対策なのか、ボードにはまばらに行政書士の事務所と個人名が入っているくらいで、ほとんどが白のプレートのままだった。
最上階は10Fだった。1部屋しかプレートを入れる場所がなかったが、その場所は養生テープでふさがれていた。テープの状態から見て比較的最近貼られたようだ。
きっと、「あの」日以降に貼られたんだろう、と僕は思った。
ふと気づくと、守衛室のカーテン越しにガードマンがこちらを気にしているようだった。ここで面倒なことになるのは避けたかった。なにしろ僕はただ「気になって仕方がない」という理由だけで詮索しているわけで、自分の行動をちゃんとした論理で説明できないのだ。
僕は多少わざとらしく、探した宛先がなかった、という残念そうな素振りをして、そそくさとビルの入り口のドアを開けて右に曲がり、自転車を停めておいたビルの南側に行こうとした。
そのとき、後ろから聞き覚えのある声がした。
「あの、すみません。この前、このビルの一番上の部屋を見ていた方ですよね。」
振り返ると、細身のカーゴパンツにパーカーを着た女の子が立っていた。
静かな朝の天気予報の彼女だった。
***
*** 第5話: 「おでん委員会」
***

文・イラスト: セキヒロタカ
「ひょっとして、斜向かいのビルのメガネ店の?」
僕はそう言ったが、彼女のことははっきり覚えていたから、「ひょっとして」は本当は不要だった。
彼女は、
「もし違っていたらごめんなさい。でも、もしこのビルの一番上の部屋を見ていたのなら、その理由が訊きたくて。ごめんなさい。」
と2度謝りながら言った。彼女はこの状況を扱いかねているのか、この前の時の静かな感じとは違って少し慌てた話し方になっていた。僕は、
「確かに僕はこのビルの一番上の部屋を見ていました。怪しまれるかもしれないけど、実は僕もはっきりと説明できる理由がないんです。自分の中ではどうしても引っかかることがあるのだけど。」
と正直に話した。なんとなく、彼女も同じようなことで引っかかっているのではないかと感じたからだ。彼女は、本当は今話したいことがあるのだけど、今日はどうしても時間がないからまた話をできる時間を作ってもらえないか、と言った。彼女は電話番号を教えようとしたが、僕は断って僕の連絡先を教えた。それから、基本的にそこで仕事をしていること、いつも僕一人だけだし、そこで寝起きもしているのでいつ電話してもらっても問題ないことを伝えた。彼女は少しだけ笑顔になり、丁寧にお辞儀をして早足で去っていった。
・・・
それから僕らは、彼女の仕事が休みの日に「その」ビルから線路沿いに少し行った駅前のドトール・コーヒーで待ち合わせをして話をした。正確には僕らの間でしか共有できない情報を交換した、という感じだ。
やはり、僕の予想通り、僕らは同じ違和感を抱えていた。
僕は、新月の前の夜、僕の部屋から見て三日月の端が「あの」ビルにかかると、最上階の「あの」部屋の明かりが必ず2度明滅することに気付いたこと、新月前夜になると「あの」部屋の窓をベランダから観察していたが、ずっと(少なくとも1年以上は)同じだったこと、それから、「あの」ビルの壁面工事が始まる前夜はいつもと違って2度明滅することなく点いたままだったこと、その明かりの色が鮮やかな緑だったこと、そして次の日突然壁面工事が始まったこと、を彼女に伝えた。
彼女は、自分には見えるが他人には見えないものがあること、それは世間で言うところの「霊感」とは少し違うような気がすること、そのことは誰にも言ったことがないこと、「あの」ビルの最上階の部屋にはずっと「変な感じ」があったこと、そして、その「変な感じ」はあの壁面工事の始まった日を境になくなったこと、を教えてくれた。
僕らはその後も何度か駅前で待ち合わせをしてそのビルに関する情報交換をした。その日も同じようにドトール・コーヒーで待ち合わせをしたのだけど、ドトールの入っている駅前の一角が改装工事に入っていた。そこで僕らは仕方なく線路沿いに自転車を押して、ぶらぶらと歩きながら話をすることにした。
線路沿いの道は、ところどころ狭いところや、片側にしか歩道がないところがあった。
僕らは歩道の狭くなっているところは縦になって歩き、広くなると並んで歩いた。夕方の渋滞が始まる時間帯で、長い列になった車のストップランプが行きかう人を赤く照らしていた。
僕らは自転車を押して歩きながらいつもとは少し違う話をした。彼女はいろんなことを話してくれた。仕事のこと、会社への往き帰りに出会った人たちのこと、会社の裏の隙間に住む野良猫のこと。
そうやってしばらく歩いていると線路沿いに大きな公園が見えてきたので、暖かい飲み物を買い、少し座って話をすることにした。暗くなってからあまり遠くまで行くのは気が引けたからだ。僕らは暖かいコーヒーとウーロン茶を買って、公園のベンチに腰掛けた。あたりはもうずいぶん暗くなっていた。
「こんな日は、おでんが欲しくなりますね。」
と彼女が言った。
「動議支持。おでんに1票。」
と僕が言うと、彼女は「満場一致。おでん可決ですね」と言って笑い、揃えた膝に手を当て、ちょっと立てたつま先を見ながら「おでん食べませんか?」と言った。
僕は「うん。いいよ。特に晩御飯の当てがあるわけじゃないし」と言って、「屋台でも行く?」と付け加えた。
「私、あそこに住んでいるんです」と彼女は言って、公園の隣のマンションを指差した。
***
*** 第6話: 「耳たぶ」
***

文・イラスト: セキヒロタカ
僕らはまた自転車を押して、線路と反対側の道を渡ったところにあるスーパーマーケットにおでんの具を買出しに行った。「暖めるだけのおでんパックでいいんじゃない?」という僕の提案はあっけなく彼女に却下され、厚揚げやちくわ麩、がんもどき、といった具材とピノ・ノワールのライトボディの手頃なワインを買って、彼女の部屋に行った。
部屋はマンションの上層階にあった。バルコニーからはさっき僕らがいた公園が見えた。
僕がバルコニーからの景色を眺めている間に、彼女は手際よくおでんの支度をし、ローテーブルにランチョンマットを敷いて食卓をしつらえた。僕は彼女から渡されたワインオープナーでコルクを抜き、グラスに注いだ。
「おでん委員会に乾杯。」
テーブルの上のおでん鍋を突付きながら他愛のない話をしていた僕たちだったが、やはり最後は「あの」部屋の話になった。
「あのビルの壁面工事の始まった日を境に「変な感じ」がなくなった、と言ったけど、正確に言うとちょっと違うの。」
彼女はそう言って、続けた。
「あの日は、私は掃除当番で早出だったので、いつもより早くここを出て、会社に行ったのね。」
彼女は少し下を向いて、おでん鍋の乗っているローテーブルの一角をじっと見つめた。
「あの線路沿いの道を歩いていると、とても胸騒ぎがしたの。私、そういうことよくあるのよ。そういうときはきまって何かある。だから、私は少し気を付けていたわ。すると、救急車がサイレンを鳴らしながら横を通り抜けていった。予感がしたので早歩きで向かったの。」
「どこに?」僕が言うと、ちょっと驚いた顔になって彼女は言った。
「もちろん「あの」ビルよ。予感がしたとおりだったわ。「あの」ビルの前に救急車が停まってた。少し時間に余裕があったので、しばらくそこで見てたの。でも、5分位して救急車は誰も乗せずに、サイレンも鳴らさずに行ってしまったの。」
僕は何も言わずに彼女の顔を見ていた。彼女はそれに促されるように、続きを話し始めた。
「それから私は会社に行って、あ、そう、言ってなかったけど、私の会社の事務所はあの店舗の上の階にあるのね、そこのロッカールームに荷物を置いて制服に着替えて、掃除をしに店舗に降りたの。店舗からは高架の下の通る道越しにビルの入り口がちょうど見えるのよ。掃除をしながらビルの前を見ると、今度はパトカーと地味なワゴンが停まってた。気になって仕方なかったので、掃除は後から超特急でやることにしてしばらく見ていたら、1人の男の人がダンボールを重そうに抱えてビルから出てきて、その箱をワゴンに積んで、パトカーと一緒にどこかに行ったの。そのすぐ後、とてもたくさんの工事車両が来たのね。あんな狭い道だからほとんど道路封鎖状態よ。たくさんの作業員の人も来て、あっという間に足場を組んで行ったわ。」
彼女は一気にそこまで話すと、ふぅと息をした。
「それから、「変な感じ」がしなくなった、ってことだね?」
と僕が言うと、彼女は「そう」と短く答えた。
「あの「変な感じ」が救急車やパトカーと関係があるかどうかはわからないけど、ただ、それを境に「変な感じ」はしなくなったの。消えてなくなるみたいに。」
「でも、不思議だな。」僕はそう言って続けた。
「僕もあの日のことが気になって、新聞記事とか警察発表とか色々調べたんだけど、「あの」ビルに関係するような記事や発表は一切なかったんだよ。ひょっとしたら何らかの公安事案だったのかもしれないね。もう少し調べてみる。きっとなにかあるはずだよね。だって、実際に警察が動いているんだから。」
僕はそこまで言ってから、グラスに少しだけ残っていたワインを最後まで飲んだ。
「ごめん、遅くなっちゃったね。帰らなきゃ。君は明日は仕事だよね。」
僕がそういうと、彼女は「明日はお休みなの」と言った。
「こんな遅いし、寒いし、今から自転車は危ないわ。それに、」
彼女は言葉を切って、僕の顔、正確に言うと目の下あたり、をしばらくじっと見つめてから、「耳たぶ。」と言った。
「耳たぶ?」
「うん。耳たぶ。触ってもいい?・・・ですか?」
「うん、いいけど。どうして?」
「これね、ある種の契約なの。」
そう言って彼女は人差し指と中指と親指で僕の耳たぶをそっと挟んだ。
***
*** 第7話: 「前田」
***

文・イラスト: セキヒロタカ
翌朝起きると、僕は一人でベッドにいた。
彼女の姿を探したが、どうやら出かけたようだった。よほど静かに支度をして出かけたか、僕が熟睡し過ぎていたか、のどちらか、またはその両方だ。
彼女は僕が寒がらないように暖房をつけたままにしてくれていたようだった。
ソファの上には、昨夜僕が脱ぎ散らかしたであろう服と下着がきちんとたたんで置いてあった。僕はそれを見て少し気恥ずかしくなり、服を着ようと起き上がりソファの方に歩いて行った。
ソファの前のローテーブルに置手紙があった。
彼女は郵便局と市役所に行く用事があること、お昼ごはんを買って帰ってくること、オーブントースターに食パンをセットしておいたのでお腹が空いたらトーストして食べてほしいということ、飲み物は冷蔵庫の中の好きなものを飲んでいいし、部屋のものは自由に使っていいということ、出る用事があったらこのスペアキーを使って欲しいということ、が書いてあり、手紙の上に部屋の鍵とオートロックの鍵が置いてあった。
僕は彼女が手紙を書いてくれているところを想像して暖かい気持ちになった。
彼女は僕が知る唯一の左利きの女の子だった。彼女はいつも左手でとても優雅に文字を書いた。空気中に浮かんでいる、まだ形になる前の言葉を、彼女が左手を通して文字にしていく様子は、まるで魔法を見ているようだった。
彼女の手紙を読み終えると、急に空腹感がやってきた。オーブントースターを開けると4枚切りの食パンがセットしてあり、コーヒーメーカーには水と挽いた豆がセットされていた。僕はオーブントースターの「トースト」ボタンを押し、コーヒーメーカーの電源を入れた。
コーヒー豆が暖められた水分を含んでいく匂いで僕の頭は少しずつ働き始めた。
重要なことは早く調べておかないといけない。物事を明らかにするには事態が安定するまでの間が重要だ。端緒から離れれば離れるほど、真実は見えにくくなる。
とりあえず、部屋に戻って今ある情報を整理し、これから調査する必要のある情報を洗い出す必要がある。
僕は、コーヒーとトーストを胃の中に入れ、食器を片付けてから、ローテーブルの上にあったメモパッドからメモを1枚切り取った。そして、用事があるのでいったん自分の部屋に戻るがまたすぐに帰ってくること、僕が合鍵を持ったままなのは良くないと思うから部屋に鍵をかけてからポストに入れておくことを書いた。それを彼女の置手紙のあった場所に置いた。そして、彼女が書いてくれた置手紙をきれいに四つ折にしてポケットに入れた。
・・・
僕は部屋に戻り、これまでのこと、彼女から聞いたこと、自分で入手した情報を整理した。自分で入手した情報は無いも同然だった。
あの日、「あの」ビルに来ていたのは、おそらく公安関係者だろう。それなら、これ以上調査するならどうしても公安事案関連の資料が必要になる。
僕は、古くからの友人の前田に連絡を取った。彼は雑誌社に記事を持ち込んでいるフリーのジャーナリストで、警察回りも長く、そこそこパイプも持っている。
携帯電話に掛けると、いつもなかなか電話に出ない奴がすぐに電話口に出た。
「お前、何か妙なこと始めただろう。」
と開口一番、前田は言った。
「どうしてそんなこと知ってるんだ?」
「オレがどれだけこの業界にいると思ってる?無警戒の素人があんな場所で毎日ウロウロしてたら誰だって気付くぞ。それでオレに連絡してきた、ってことだろう?まぁ、どんな用件かはおおよそ見当が付く。少なくともピクニックのお誘いでないことくらいはわかる。」
「それなら話は早い。教えてほしいことがあるんだ。」
「電話は駄目だ。場所を決めて会おう。FAX で送る。FAX の番号を教えてくれ。」
僕が FAX 番号を教えると、「そのままそこで待て」と言って前田は電話を切った。
しばらくすると、FAX で待ち合わせの場所が送られてきた。隣の市の中心から少しだけ歩いた所にあるスターバックスに1時間後、徒歩で来い、というものだった。降りるバス停も指定されていた。FAX の発信元から見るとどうやら、近くのコンビニエンス ストアから送ったようだった。かなりの念の入れようだな、と僕は思った。
僕は早速着替えて(それまで僕は昨日の服のままだったのだ)、隣の市の中心地に向かった。バスを2本乗り換えて、指示されたバス停で降り、スターバックスに向かった。
そのとき、携帯電話が鳴った。前田からだ。
「こちらから、お前の姿が見えるよ。」
「どこにいるんだ?」
「いいか、スターバックスを通り過ぎてすぐの交差点で道を渡れ、向かいの映画館の隣の喫茶店の窓際にいる。」
僕は四車線道路の歩行者信号が青になるのを待って渡った。喫茶店はミニシアターの陰になったところにあった。昔ながらの、という感じの喫茶店だ。
ドアを押して入ると、ドアベルが「からんからん」と鳴った。
右を振り向くと、そこに前田がいた。
僕は表情をなるべく変えないようにして向かいに座り、ダッフルコートを脱いで隣の席に置いた。
注文を取りに来た女の子にホットのブレンド コーヒーを注文してから前を向くと、前田は俯き加減で顔をしかめながらタバコに灯を点け、マッチを振って火を消していた。
「最近マッチがなかなか手に入らなくてねぇ。そのために喫茶店に来ているようなもんだ。」
「スタバにはマッチはないからな。」と言って僕は笑った。
前田はちょっと苦笑いを浮かべたが、真顔に戻って言った。
「俺から言えることは、あまり深入りするんじゃない、ってことくらいだ。」
「いや、深入りしようと思っているわけじゃないんだが、進行中の公安事案を調べる方法はないかなと思ってね。」
そう言って僕がいきさつを話すと、前田は指に持っていたタバコをくわえなおし、諭すような口調で話し始めた。
「警察には捜査情報を保存しているシステムがあるのは聞いたことがあるだろう?内部の人間は“TOP-WAN”と呼んでるが、当然、アレには部外者はアクセスできん。警察内部でも端末で検索できる範囲は階級ごとで限定されてるくらいだからな。政治マターになる可能性のある事案なんて、アクセスできるのはごくごく一部の人間だ。TOP-WAN はクローズドなネットワークで運用されていて、インターネットには接続されていないから、ハックも無理だ。」
前田は少し間を空けてタバコの煙を吐き出し、1/3位残ったタバコを灰皿に押し付けながら続けた。
「警察官はリークがバレたらクビだからな。何の得もないのにリークはせん。特にその手のヤバい事案はな。警察官は退職しても守秘義務が掛けられているからそっちの線も無理だ。事件を担当した弁護士から情報取ろうにも、そもそも立件されていないわけだからな。それも無理だ。」
前田は、タバコの箱を取り出して、トントンとテーブルの端を叩き、また1本タバコを取り出して口にくわえた。マッチ箱を親指と人差し指で挟んで手の中で回しながら、何かを考えているようだった。
「あのビルから運び出されたブツ、どこに送られたと思う?」
タバコに灯を点けないまま前田はそう僕に訊いた。僕は黙って前田の顔を見ていた。
「SPring-8 さ。」
前田はそう言うとタバコに灯を点け、大きく煙を吸って吐いた。
「その後、和光の方に送られたらしい。まぁ、そういう事案ってことだ。」
前田はそう言って、「とにかく気をつけたほうがいい」と言った。
僕たちは残っているコーヒーを一口だけのみ、席を立った。
僕はノー ギャランティーで前田の時間を拘束したことを侘び、そのうち何らかの形で返す、と言った。前田はタバコをくわえたまま、
「この店を出たら、お前は左へ行ってバスに乗れ。」と小声で言った。
僕は、無言で頷き、前田より先に出て左に曲がった。
交差点で信号待ちをしている間、横目で前田を追った。
彼はそのまま右に曲がり喫茶店の奥の路地に入っていった。その間、こちらを見ることはなかった。
・・・
時計を見るともうすでに夕方だった。
僕は慌てて、彼女のマンションに向かった。
オートロック端末のテンキーで部屋番号を入力したが応答がない。電話を掛けてみようと携帯電話を取り出すと電源が切れていた。僕は1日半くらい充電をしてなかったことに気付いた。なんてこった。いつもはこんなヘマはしないのだけど。
合鍵をポストに入れたので、部屋に入っているわけにも行かない。僕は待つしかないのだ。
部屋で待つのもここで待つのも変わりないかと、コーヒーを買って近くの公園に行きしばらく時間を潰すことにし、マンションの正面の階段を下りようと振り返ると、階段の下に彼女がいた。
***
*** 第8話: 「砂の日」
***

文・イラスト: セキヒロタカ
「私がどんな気持ちで待っていたかわかる?ポストに入っていた合鍵を見て、どんな気持ちになったかわかる?」
「ごめん。もっと早く戻ってこようと思ってたんだよ。不安にさせたり心配させたりしたのは、本当に悪いと思う。ごめん。」
彼女は、俯いたまま左手で僕の右手の指先をぎゅっと握った。
「公園、行こうか。暖かいものでも飲みながら、少しお話しよう。」
僕がそういうと、彼女は握った僕の手を見ながらだまって頷いた。
僕たちは公園の入り口にある自動販売機でコーヒーを買い、手をつないだまま公園を横切ってベンチに腰掛け、暖かい缶コーヒーを分け合った。日は少し長くなり、公園では花も少し咲き始めていた。
僕たちは、ベンチに腰掛けたまま、野良猫の毛並みの差や公園の木の枝ぶりについて、ぽつぽつと話をした。
僕は前田から聞いたことを話さなかったし彼女も訊かなかった。多分、二人ともそんなことを話すのは何か違うような気がしていたのだと思う。
僕はくだらない冗談を言い、彼女は笑った。
「あなたって、そういうこと言わない感じなのにね。そういうくだらないところも好きよ。」
いつものように彼女はそろえた膝に手を当て、ちょっと立てたつま先を見ながらそう言った。
僕は暮れてきた空を見上げた。
さっきまで真っ青だった空は濃い群青になり、少し筋雲が掛かっていた。
・・・
公園から戻った僕たちは夕食も取らずにセックスした。
お互いの中にできた大きな空洞を埋めるように、お互いを食べ尽くすように貪り合った。
途中、オートロックのインターホンが一度鳴った。
彼女は、小さな声で「やめないで」と言って、僕の両頬を引き寄せて深いキスをした。
彼女は何度も達し、僕も果てた。
・・・
僕は彼女に今日前田から聞いたことをゆっくりと話した。
すでにあのビルの周りは当局から監視されていること、彼女が見たビルから運び出されたダンボール箱は SPring-8 へ運ばれた後、理研の和光本所に送られたこと。
僕が話し終わっても、彼女は僕の胸に顔を付けたままでじっとしていた。
しばらくして、少しずつ今日あったことを話してくれた。
「“あの”部屋にいた人たちは私たちからは感じられないところに行ってしまったと思うの。もうこの世界にはいない。この世界のどこにもいないの。」
彼女はそう言って、僕のうなじに鼻先を軽く当てた。
それは嗅覚で僕との記憶を固定しようとしているように思えた。
彼女は話を続けるのを少しためらっているようだった。
「今日、お昼前に部屋に帰ったらあなたがいなかったから部屋で待っていたのね。でも、なかなか帰ってこないので、きっとあのビルのところに行ったんだ、と思って自転車でビルのところに行ったの。今日もやっぱりあの“変な感じ”はしなかったわ。少しビルを見上げていたら、視線を感じたの。外国人の男の人と多分日本人の男の人がこちらをじっと見てた。私、少し怖くなって急ぎの用事があるフリをして自転車で急いで帰ってきたの。」
彼女はそういってから、僕のうなじから顔を離した。
やはり、当局の監視が厳しくなっているようだった。彼女もマークされかねない、と僕は心配になった。
「職場が近いから難しいだろうけど、もうあのビルに近づくのはやめた方がいいよ。君が危ない目に遭うのは耐えられないよ。」
「うん。わかったよ。」
彼女はそう言って僕の胸元に顔を戻し、それから、身体を少し起こして首の後ろに手を回してネックレスを外した。僕は彼女がそのネックレスを外したのを初めて見た。そのシルバーのトップの付いたネックレス (正確に言うとペンダント、だ) はいつも彼女の胸元にあった。シャワーのときも、眠るときも。僕と抱き合うときも僕と彼女の間にネックレスがあった。だからそれは僕にとってずっと彼女の一部であったし、僕らの“一員”だった。
彼女はまたゆっくりと身体を僕の方に倒し、僕の首に優しく手を回してネックレスを着けた。それから彼女は僕の右の頬に唇を静かに付け、目を閉じてしばらくそのままにしていた。その間、彼女の柔らかな乳房がずっと僕の腕に触れていた。彼女は目を開けると、「そのネックレス、あげる。いつか、そのネックレスがあなたに必要になるときが来ると思うから。」と言った。
僕には彼女の言っている意味が分かった。彼女には見えるのだ。
そのとき僕は身体の中の「心」の場所が分かった気がした。その場所が強く締め付けられて湧き出た感情が僕の身体をいっぱいにした。僕は彼女を両腕で抱きしめた。僕の中からこぼれた感情は海岸の砂のようにサラサラと彼女の頬の上を流れた。
「あなたは大丈夫よ。」
彼女はそう言った。
・・・
僕は夢を見ていた。
僕たちは砂の惑星にいた。
砂でできた部屋に住み、砂色のベッドで寝ていた。
世界はすべて砂色の濃淡でできていた。
「次の新月の夜は、砂の日ね。」
と彼女は言った。
・・・
僕は激しい胸騒ぎで目が覚めた。
とっさに彼女の姿を探そうとしたが、その必要はなかった。
彼女の吐息で僕の胸の辺りは暖かく少し湿っていた。
僕は安心して、彼女が目を覚まさないように気を付けながら彼女の肩を静かに抱いてまた眠った。
・・・
朝になり、僕たちは一緒にシャワーをして、僕は彼女に部屋にいるように言ってから、朝食を買いに出た。
僕らは昨日の昼から何も食べていなかったし、彼女が昨日昼ごはんにと買って来てくれたイタリアン・レストランのピザはすっかり冷えて硬くなってしまっていた。
僕は彼女を部屋に残しておくのはとても心配だったが、僕と一緒に動き回るのはもっと心配だった。僕はすばやく食パンとミネラルウォーターとヨーグルトを買ってマンションに戻ろうとレジに並んだが、2人前の客のクレジットカード・エラーでレジの列は渋滞していた。
何とかレジで支払いを済ませてマンションに戻り、オートロックを鍵で開けて、エレベーターで彼女の部屋の階まで昇った。エレベーターはとても遅く感じられた。
部屋の鍵を開けようとしたが、部屋の中から彼女が出てくる気配がない。僕は動悸を抑えて急いで部屋に入った。
彼女の姿がなかった。
僕は慌ててトイレをノックした。トイレの電気も消えていた。もちろん彼女もいなかった。
ローテーブルに彼女の短い置手紙があった。
「一緒に朝ごはんが食べられなくてごめんなさい。少し出かけるので、自分のお部屋に戻っていて。私も戻ったら連絡するから心配しないで。いつも愛しているわ。」
僕は昨夜のことを思い出して、急いでオートロックのインターホンの所に行って録画再生ボタンを押した。
「録画件数 0 件」
しまった!なんてこった!こんなときにこんなボーンヘッドするなんて!
0件である訳がない。昨夜、インターホンが鳴ったのは間違いないのだ。
誰かが、何らかの目的で録画を消したのだ。
彼女を一人で残した悔いと自分に対する激しい怒りがこみ上げてきた。
「なんてこった!」
僕は何度もそう吐き捨てた。
***
*** 第9話: 「消失」
***
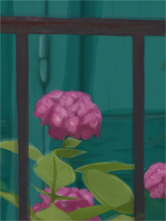
文・イラスト: セキヒロタカ
僕は彼女に繋がっている糸の先をなんとか見つけようとしたが、彼女自身のこと以外は具体的に何も知らないことに気付き愕然とした。
彼女の実家のこと、彼女の病弱な両親のこと、彼女の昔の友達のこと。もちろん、大まかなことは知っていた。両親はどういう人で、どういうところで育って、どういう友達がいたか、は知っていたけど、じゃあ、名前は?住所は?電話番号は?
何も知らなかった。
部屋の中を探せば何かが見つかるかもしれなかったが、彼女がいない間に家捜しするのはフェアじゃないし、彼女を冒涜するような気がした。
僕は彼女の置手紙を丁寧に四つ折にして、傷まないようにブルゾンの胸ポケットにしまった。今の僕にとっては、この彼女の手紙以上に大事なものはないように思えた。
僕は急いで部屋を出て鍵を閉め、エレベータの下行きボタンを押したが、ちょうど下の階に通り過ぎてしまったところだった。
僕は階段を駆け下りてマンションの駐輪場まで行き、自分の自転車を探した。自転車は予想通りパンクさせられていた。僕はタクシーを拾って、運転手に彼女の職場の場所を告げた。
彼女の職場の雑居ビルの周りは渋滞していた。僕は途中でタクシーを降り、走った。
朝で客もまばらな1Fのイタリアンカジュアルの店を早足で通り抜け、エレベーターホールにたどり着いた。
僕は、1Fに停まっていたエレベータに乗り、「6」を何度も押した。
僕は最悪の状況も覚悟していたが、メガネ店は営業していた。ガラス張りの店舗を通って来た朝日で明るくなったエレベータホールを見て、気持ちが少し落ち着いた僕は、店の中で話す内容を整理した。僕は一度深呼吸をして、ガラスのドアを開けて店に入り、まっすぐカウンターに向かった。
もちろん、そこには彼女はいなかった。
カウンターの女の子が僕に気付いて笑顔で挨拶したが、僕の表情を見てメガネを買いに来た客でないことをすぐに理解したようだった。
僕は、その女の子に彼女の名前を告げ、彼女が今朝、朝食も摂らずに突然いなくなったこと、詳しくは言えないが彼女が事件に巻き込まれているかもしれないこと、を話し、もし彼女か彼女の代理の人間から連絡があったら、もう例の調査はやめたということと、可能なら僕まで連絡して欲しいということを伝えてくれるよう頼んだ。
次に職場に電話してくるとしたら、おそらく彼女ではなく連れ出した連中だろう。僕が例の件を嗅ぎ回るのをやめたことが分かったら、彼女を早く解放するかもしれない。
彼女のプライベートなことを彼女の同僚に話すのはとても抵抗があったが、そんなことを気にしている余裕はなかった。
その女の子は彼女とそれほど親しいわけではないようだったが、真剣な表情で僕の話を聞いて「警察に連絡しましょうか?」と言ってくれた。
僕は、それはこちらでやりますから、と断り、協力してくれてありがとう、と言って店を出た。
・・・
雑居ビルから出ると、いつも通りの風景があった。
でも、そこには彼女はいない。
僕のせいで彼女はこの風景から取り除かれてしまったのだ。
僕は、本来いるべき場所から猛スピードで遠ざかっていることを感じていた。
僕という惑星は、突然、彼女という太陽を失い、宇宙の辺縁へ弾き飛ばされていた。
気付くと僕は雑居ビルの前の横断歩道を渡っていた。
鉄道の高架下を通る道の向こうに、足場が取り外された「あの」ビルが見えた。
僕は、ビルの変化に気付いた。
「あの」部屋の窓がなくなっていたのだ。
壁面からは窓が完全になくなって、他の壁と同じ材質で覆われ、何かの看板を取り付けるためのステーが設置されていた。
どうして東側の窓をふさいでしまわないといけないのか、僕には理解できなかった。ターミナル駅近くとはいえ、線路側の看板にそれほどの広告効果があるとは思えなかった。
理由は僕にはわからなかったが、「その」窓の存在が痕跡を残さずにこの世界から消えたのは明白な事実だった。
でも、今の僕にはそんなことはどうでも良かった。
少し前なら、そのことに驚愕し、大きな疑問を感じただろうけど、それより、こんなことに彼女を巻き込んでしまった自分に腹を立てていた。
彼女は職場が近いこともあったし、僕がとても「あの」部屋に興味を持っていたので、頻繁に ― 日によっては何度も ― あのビルを見に行ってくれていた。
しかも彼女は何かを感じるから、余計に目立ってしまったのかもしれない。
もし僕が、彼女にあんなことを言わなかったら、彼女は今でも普通に暮らせていたかもしれないのに。
悔やんでも悔やみきれなかった。
・・・
「ということは、当面お前と俺は大丈夫、と言うことだ」
電話に出た前田はそう言った。僕たちは情報を持たず嗅ぎ回っている側と見做された、と言いたかったのだろう。
「当局が動いたのか?」
「それは俺にもなんとも言えん。とにかく俺は手を引く。お前ももうこの件にはかかわらない方がいい。」
前田は僕の質問に手短に答え、そのまま電話を切った。
・・・
彼女を連れ出した連中が当局でないこともあり得たので、警察に連絡することも考えた。だが、取り合ってくれるわけがなかった。表面上はまったく事件性がないのだから。交際相手の女性が「すぐ戻る」と置手紙を置いて外出しただけ、なのだ。取り合ってくれたとしても、まともに捜査してくれるとは思えないし、もし動いたのが当局なら彼女が解放されるのが遅れるだけかもしれない。
そのとき、僕はようやく、重要なことを忘れていることに気付いた。
僕は大急ぎでタクシーを拾って、彼女の部屋に取って返した。
・・・
遅かった。
彼女の部屋はすっかり空っぽになっていた。部屋越しに見えるバルコニーの隅にもたれかかるように、小さなポトスの鉢だけが残されていた。僕は急いで部屋を出て前の廊下から下を見た。ちょうど、引越し業者のトラックが出て行くところだった。
僕は遠ざかっていくトラックをただ呆然と見送るしかなかった。
・・・
僕は彼女の部屋に入って、小さなポトスの鉢を大事に抱え、今朝までローテーブルが置かれていた場所に座った。
空っぽになった彼女の部屋はとても小さく感じた。
僕はポトスを抱えながら、彼女と、彼女といた部屋を思い出していた。
かすかに彼女の匂いがするソファとクッション、こじんまりとしたローテーブル、ソファに寝転んで笑う彼女、おでん鍋とピノノワールのワインボトル、彼女の体温で暖かくなったベッド、彼女の寝息で湿った僕の胸。
僕は胸ポケットから四つ折にした彼女の置手紙を取り出して広げ、何度も何度も読んだ。彼女がくれたペンダントのトップがポトスの鉢に触れて「チン」と鳴った。
気付くと僕は声を上げて泣いていた。
・・・
「すみません。そこにおられるのはどなたですか?」
玄関の方から声がした。管理会社の担当者のようだった。
「勝手に入られると困るんですよね。」
僕は、慌てて涙を拭いて玄関に行き、合鍵を見せて怪しいものではないことを説明した。そして、合鍵は返すから思い出の品のポトスは持って帰ってもいいか、と訊いた。キーシリンダーは交換されてしまうから持っていても仕方ないし、持っていることでまずいことにもなりかねない。それに、僕にはこのポトスの鉢は彼女と繋がる大切なものだった。
「本当は困るんですけど、何も見なかったし、聞かなかったことにします。」
彼は僕のことを交際相手に捨てられた哀れな男と思ったのだろう。少し同情してくれたようだった。
「これ、使います?」
と彼は手に持っていた紙袋を僕に差し出した。僕は礼を言って、その紙袋にポトスの鉢をそうっと入れて抱えた。彼は、もう閉めるので申し訳ないが出て行ってもらえないか、と僕に言った。僕はもう一度礼を言って廊下に出た。
・・・
いつの間にか、少し陽が傾きつつあった。
廊下から見えるビル群は、傾いた太陽に照らされて金色に輝いていた。
風は、春の夕暮れの、少し甘くて、不透明な匂いがした。
***
*** 第10話: 「声」
***

文・イラスト: セキヒロタカ
気付くと、いつの間にか夏も終わろうとしていた。
僕は半年の間、毎日彼女と繋がる糸の先を探し続けた。新たに入ってくる仕事はすべて断った。とても仕事ができる精神状態ではなかったから、受けてもできなかっただろう。
・・・
夏の湿度を含んだ空気が、秋の乾いた空気に入れ替わったころ、例の SPring-8 に送られた検体の件で米DHSのテロ対担当が日本に入り警視庁公安部のNBCテロ対応専門部隊と連携していたという噂が聞こえてきた。前田が手を引くのも理解できた。予防検束まがいのこともあり得る、と考えたのだろう。
僕は、彼女がいなくなる前日に「あの」ビルの前で「外国人と日本人と思われる二人組から見られていた」と言っていたことを思い出した。彼女は、あのビルの様子を毎日(日によっては何度も)観察しに行ってくれていたから彼らにとっては明らかに不審人物だ。
予想されていたことだが、すでに彼女は自己都合で退職したことになっていた。彼女の職場に実家の連絡先を訊いたが、もちろん答えてくれるはずもなかった。
前田の推測が正しければ、僕一人でなんとかできる問題ではなかった。ただ、静かにして僕は何も嗅ぎまわったりしないし、彼女が帰ってきても何も詮索する気はない、ということを「彼ら」に理解させることが大事だった。
・・・
そして、彼女が居なくなって2度目の冬が来た。
彼女と時間を共有していた季節。
彼女と最初におでんを食べた曜日には、僕は必ず、テーブルの上にポトスの鉢を置いて、おでんを作り、ピノノワール種のワインを買い、一人で飲んだ。
ある日、僕の部屋のオートロックのインターホンが鳴った。
インターホンのカメラの向こうには、特徴のないビジネススーツを着た、特徴のない顔立ちの三十歳前後の男がいた。その男は、僕の名前を知っていた。
僕はとても警戒していたが、その男は自分の名前を名乗り、彼女の弟だと言い、姉からの預かり物を持ってきた、と言った。
僕は驚き、オートロックを開け、彼を玄関まで招き入れた。
彼女からの預かり物とは、僕宛の手紙だった。
手紙には、「一緒に朝ご飯食べられなくてごめんなさい。あなたとまた一緒に朝ご飯を食べたかった」と書かれていた。
間違いなく彼女の筆跡だった。僕は毎日彼女の2通の置手紙を読んでいるから、間違えるはずもなかった。
「この手紙は、姉から生前、あなたに渡して欲しいと、預かったものです。」
と彼女の弟は言った。
精神を患った末の自殺死だった。
彼女の弟が帰って、一人になった僕は、声を上げて泣いた。
声を抑えようと思ったが、無理だった。
僕はベッドにもぐりこみ、枕を口に押し付けて、大声で泣いた。
・・・
そして、僕は、うつになった。
それは中途覚醒から始まり、そのうち、平衡感覚が保てなくなった。三半規管から入ってくる膨大な情報量に、うつで傷んだ脳が耐えられなくなったのだ。
次に、テレビなどの動く情報を受け入れることができなくなり、音楽も聴けなくなった。観たり聴いたりするだけで、脳が処理できずにパンクして、頭がぐらぐらし吐き気がするようになった。
わけもなく一人で突然号泣してしまうことがあり、外出はほぼ不可能になった。階段の上り下りでさえ安全に遂行できなかったので、いずれにせよ外出は難しかった。
知人の精神科医から、すぐに専門医に見せた方が良い、僕でも良いができれば個人的な知り合いじゃない方が良いだろう、と言われ、彼と留学先が同じで信用できる精神科医を紹介してもらった。
比較的有効性が高いと言われていた SSRI を何種類も試し、承認されたばかりの SNRI も試した。前世代の三環系抗うつ剤も試した。しかし、どれも焦燥感を高めたりするばかりで何の効果もなかった。
僕は毎日、朝早く、というより夜中に目を覚ました。
意識がはっきりすると、とにかく自分の真中あたりがものすごい力で締め付けられるように強烈に痛んだ。肉体の苦痛とまったく同様に、精神の苦痛も「痛覚刺激」を伴うということを初めて知った。僕はその痛覚を麻痺させ、苦痛を和らげるため、毎日大量の安定剤を飲んだ。そして、一日をぼんやりと過ごし、夜、ベッドに入ってから意識を失う程度の量の眠剤を飲むこと以外、毎日ほとんど何もせずに過ごした。
体重は激減し、預金口座の残高は確実に減って行った。
あまりの苦痛に(実際に「痛む」のだ)、僕はそれから解放される一番簡単な方法を選ぶことにした。ホームセンターに行ってロープを買い、枝ぶりの良い木を探しに長い距離をふらふらと歩いて(車を運転できる状態ではなかったから歩くしかなかったのだ)山に入った。
僕は夜の山の中をふらふらと歩きまわり、疲れたら木の根元に座って、森の声を聴いた。
夜中の森の中では、自分の体と森との境目がとても曖昧になる感じがする。いや、実際に曖昧になるのかもしれない。僕は月明かりの中、目を凝らして、森との境目が曖昧になった僕の両手を眺めた。その行為自体、特に意味を持つものではなかったが、僕はそうしながら、僕の意思に付随して動くものがこの世にあることの不思議さを考えていた。
一晩中、森の声は止まなかった。その声は、限りなく透明でおぞましい声だったが、僕は恐怖を感じなかった。恐怖とは自分から何かを奪われることに対する感情だが、僕には奪われて困るものは残念ながらなかった。
僕はその声を聞きながら目を閉じた。
そして、僕はまた“砂の日”の夢を見た。
・・・
砂の惑星に住む僕たちは“砂の日”にその街に出かけることになった。
途中の街で、僕たちはドトールコーヒーに入って、アイスラテのショートサイズを 2 つ注文し、いつものように、通りに面した窓際のバーに並んで座った。
「あなたは“砂の日”が嫌い、って言っていたけど、」
彼女はそう言って、アイスラテの氷をストローでぐるぐるとかき混ぜた。
「私はそれほど嫌いじゃないわ。」
「『分かるよ』なんて軽々しく言えないけど、分かる気がする。“砂の日”なんかにあの街に行くなんて、誰とでもできるものじゃない。でも、僕たちは二人でこうして“砂の日”にあの街に行こうとしている。そういうことだよね。」
僕も、彼女と同じように氷をかき混ぜながら言った。
彼女は、ラテのストローを手に持ったまま、猫がそうするように、僕を見たまま黙っていた。僕たちはお互いに何か言おうとしたけど、結局あきらめて、窓の外のアンバーグレーにかすんだ空を眺めることにした。
僕の左手の小指に何かが触れた。見ると、彼女が人差し指を僕の小指の上に乗せていた。
「幸せというのとは違うけど、」
彼女は、僕の左手を見つめて言った。
「あなたといられて良かったと思う。」
僕は「僕もだよ」と言おうとしたけどやめた。そんなことはとっくに君は知っているだろうから。
外では相変わらず強い風が吹き、世界は砂の色の濃淡だけで構成されていた。
僕たちは、砂の惑星の知らない街のドトールの窓際で、人差し指と小指でつながっていた。
・・・
彼女がいなくなる前の夜に見た夢の続きだった。
目が覚めても、まだ森は暗かった。
僕は彼女がくれたシルバーのペンダントのトップを壊れやすいものを扱うように握っていることに気付いた。
手のひらをそっと開くと、シルバーのトップが淡い緑色に光った気がした。森の木の間から差し込んでくる仄かな月明かりが反射したのかもしれない。ただ、僕にはそれ自身が光を放っているように見えた。
僕は、精神の痛覚刺激が少し和らいでいることに気付いた。
そのシルバーのトップは、まだその時ではないよ、という彼女からのメッセージを送っているようにも感じられた。
ぼんやりしているうちに、空の色が急に変わった。森の夜は唐突に終わり、朝がやってきた。
もう、森の声は聞こえなかった。
僕は、山を下り、ふらふらと来た道を歩いて、部屋に戻った。
・・・
部屋に戻った僕は、彼女の部屋から持って帰ってきたポトスの鉢を落とさないように大事に抱えて、ベッドに腰掛けた。僕は目を閉じてポトスの鉢を両手で包み、そこにかすかに残っている彼女の体温を感じ取ろうとしていた。
彼女がくれたペンダントのトップがポトスの鉢に触れて「チン」と鳴った。
彼女のからっぽの部屋で、この鉢を手のひらで包んでいたときのように。
その時、朦朧とした頭の中で、ずっとモヤモヤしていた二つの情報が繋がった。
僕は二重になっている鉢の内側の鉢を静かに外側の鉢から抜いた。
***
*** 第11話: 「確信」
***
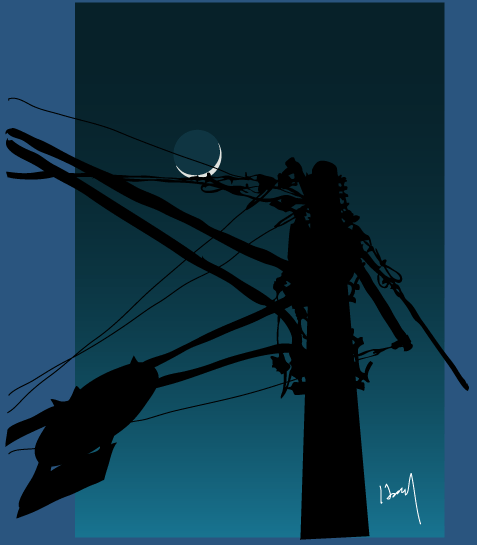
文・イラスト: セキヒロタカ
僕は注意深く外側と内側の鉢を観察したが、特に変わったところは見つからなかった。
思い過ごしか、と鉢を元に戻そうとしたとき内側から擦るような音がかすかに聞こえた。僕は静かにポトスの株を覆っているウッドチップを退かしていった。
「それ」は、鉢の内側に張り付く形でウッドチップに見せかけたプラスティックに覆われて置かれていた。静かに剥がすと、張り付いた面にはピエゾピックアップに使われるようなラバーが付いていた。「その手」の機器に詳しくない僕が見ても明らかに「隠すため」の造りだった。
「外事か。」
僕は声に出さずにつぶやいた。おそらくこれは盗聴器だろう。
僕は盗聴器を発見したことに何の感情も抱けなかった。今頃盗聴器を発見しても遅いのだ。何もかも終わってしまった。
そのウッドチップ状のプラスティックはずいぶん汚れていた。おそらく、僕の部屋に来てから仕込まれたり、電池交換されたりしたことはないだろう。多分、すでにバッテリーも切れて機能もしていないはずだ。彼女を予防検束した後の数日間、僕の行動を監視するためのものだったのだろう。
あの管理会社の担当者も当局の人間だったのかもしれない。もともと、ポトスの鉢だけが残されていたこと自体不自然だったが、彼女の部屋が空っぽになったショックでそこに気が回らなかった。もし僕がポトスの鉢を持って帰ることを申し出なかったとしても、忘れものとして手渡すためにあのタイミングで現れたとも考えられる。そう考えると、彼女がいなくなった朝に、レジでクレジットカードエラーの渋滞を作っていたのも同じ連中かもしれない。
ちょっと待てよ、と僕はそこで気付いた。
「彼女の弟?」
そんな、バカな。
僕は彼女の両親のことは聞いたが、弟のことは一回も聞いたことがない。
いるなら、きっと僕に話しているはずだ。
僕はその時、ずっと抱いていた違和感が頭の中でほどけていくのが分かった。
僕は「彼女の弟」と名乗る男が持ってきた彼女の手紙を取り出して、彼女の置手紙と比べた。
どれもボールペンで書かれていた。筆跡は彼女のものだ。少なくとも僕にはそう見える。
僕はそれまで、彼女の最後の置手紙と「彼女の弟」が持ってきた手紙の文面がよく似ていることに少し違和感を感じてはいた。
しかし、違和感の本当の理由がはっきりした。
「彼女の弟」が持ってきた手紙だけ、ボールペンの「インク溜り」の跡が違っていたのだ。「彼女の弟」が持ってきた手紙の「インク溜り」は、その手紙を書いたのは右利きの人間だったことを示していた。
「そういうことか。そういうことか!」
僕は安定剤の残るぐらぐらした頭を必死で覚醒させながら、声に出さずに叫んだ。
・・・
僕はまた砂の星の夢を見た。
彼女からこのペンダントをもらってから、僕は砂の星の夢を見るようになった。
最初に見たのは、ペンダントをもらった夜だ。
彼女がいなくなる前の夜。
砂の星の夢。
多分、これは夢なんだろう、と思う。
・・・
僕と彼女は宇宙船に乗っていた。
外には、僕たちの星、砂の惑星が見える。
僕たちは、遠く離れた惑星に派遣されるのだ。
僕たちは、人工冬眠で冷凍されてその星までたどり着く。
だから、到着したときには、僕たちの星ではもう僕たちの家族も友人も生きてはいない。それを理解しての任務なのだ。
僕たちの星は滅びつつあった。
居住可能な他の惑星を見つける必要があった。
故郷の星を離れれば、再び故郷の者と会う可能性は極めて低い(居住可能な星がすぐに見つかって、すぐに移住しない限り)。孤独な任務だが、誰かがやらねばならない任務だと誰もが分かっていた。そして、僕たちの星は、大きな多細胞生物のように、星の住民と星そのものが意思を共有していた。
多くの若い住民は孤独な任務を帯びて遠い宇宙に旅立っていった。
僕たちも同様だった。でも僕たちは特に孤独だとも思わなかった。僕たちが必要としたのはお互いだけだった。
僕たちは、人知れずその遠い星の調査を行い、そして、僕たちは、僕たちのルールで、その惑星の新月の前夜、遠い遠い故郷の星に向かってメッセージを送る。
故郷の星にはもはや自分たちの知る人は誰もいない、ひょっとしたら星自体が今はもうなくなっているかもしれない故郷に。
・・・
目が覚めると、僕はシルバーのペンダントトップを握りしめていた。
手のひらをそうっと開くと、ペンダントトップがまた緑色に光った。この前と違って今回はもっとはっきりと光った。部屋の壁がその光を反射して、少し緑色に見えた。
そして、僕は、今日は新月の日、つまり、砂の日だ、ということに気付いた。
***
*** 最終話: 「新月前夜、窓、そして君の事。」
***

文・イラスト: セキヒロタカ
その日は、どんよりと曇っていたが、2月とは思えない暖かく乾いた風が吹く日だった。
僕は、駅前のドトールコーヒーに向かっていた。
頭はまだ眠剤と安定剤でぼんやりとし、足元はふらふらしていたが、僕はドトールへ向かった。
途中、車道側に倒れそうになり、それに驚いて怒鳴るタクシーの運転手に謝り、赤信号に気付かずに横断歩道を渡って大型ダンプに巻き込まれそうになりながら、僕はドトールへ向かった。
「今日は砂の日だ。今日は砂の日だ。」
僕は歩きながら、心の中でそう言い続けていた。
・・・
ドトールに入って、僕はすぐに窓際のバーテーブルの方に目をやった。
バーテーブルには、サラリーマン風の男が1人腰かけて、モバイルPCのキーボードをせっせと打っていた。
僕は心底がっかりし、そんなに物事上手くいくわけはない、と心の中でつぶやいた。
僕は、ブレンドコーヒーのショートサイズを頼んで、窓際のバーテーブルに運んだ。特にコーヒーが飲みたい、というわけでもなかった。それに、僕は抗うつ剤の影響でカフェインに過剰に反応してしまうのだ。
僕は、トレイの上のコーヒーカップに触れることもなく、ただぼんやりしていた。
そのとき、彼女からもらったペンダントのシルバーのトップがカップに当たって、ちん、と音を立てた。僕は、はっと、我に返り、目の前のガラスの向こう側から来る視線に気付いた。そこには、こちらをじっと見て立っている女の子がいた。
彼女だった。
僕は店を飛び出して、彼女に駆け寄った。
急がないと、何かが変わってしまうかもしれない、そんな気がした。
店員や店の客は、きっと驚いてこっちを見ていただろうが、全く目に入らなかった。
僕は無言で彼女を抱きしめた。彼女も僕を強く強く抱きしめた。
そして、長く長く深いキスをした。
・・・
やはり、彼女には弟はいなかった。僕の部屋を訪ねてきた男は彼女の弟ではなかったのだ。もちろん、彼女の手紙も「左利き」の彼女が書いたものではなかった。
彼女は精神病院に入院していた。彼女が国際テロとの関係を疑われて予防検束されたあと、病気がちだった彼女の父親は死に、3ヶ月後母親も死んだ。
心のバランスをひどく崩し、食事も取れない状態になった彼女は、そのまま精神病棟に入ることになった。
1年以上の入院生活の後、NDA に署名をすることを条件に3か月前、彼女は外出許可を得た。
「あなたの部屋に直接行くと迷惑がかかるかもしれない、と思った。少なくとも「彼ら」はそう言ってたから。」
「あなたとあの部屋にいた最後の朝、前の夜に見た「砂の日」の夢の話をしてくれたのを思い出して、毎月、新月の日に外出許可を取ってここに来ていたの。このドトールに来ていればきっとあなたは来てくれると思っていたわ。」
「酷い連中だ。何が迷惑なもんか。君が傍にいないこと以上に耐えられないことなんて、この世にあるわけがない。」
僕はそう言って、また彼女を抱きしめた。
・・・
僕たちは、手をつないで、線路沿いの道を僕の部屋まで歩いた。
僕は、初めて彼女と自転車を押して歩いた日のことを思い出していた。きっと彼女も同じだっただろう。
僕たちは、何も話さなかった。
話す必要もなかった。
僕たちは、一緒にいる。そして、同じ道を手をつないで歩いている。
少なくとも今は。
それがどれだけ貴重なことなのか、どれだけ幸せなことなのか、今はとても分かる。
未来のことは分からない。
でも、今、一緒にいられること、それが何より大事なんだ。
僕たちは、同じ気持ちで、線路沿いの道を歩いていた。
「こんな日は、おでんが欲しくなるね。」
彼女が言った。
「動議支持。おでんに 1 票。」
僕はそう言った。僕たちは、じゃあ、おでん可決だね、と笑った。
僕たちは久しぶりに、本当に久しぶりに心の底から幸せな気持ちになった。
さっきまでどんより曇っていた空も、気が付くと西の方から青空になって来ていた。
線路の架線の西日に照らされた面が、きらきらとオレンジ色に光っていた。
僕は、僕たちが存在する世界中の景色がとても懐かしいものに思えた。
僕たちは、「本来いるべき場所」に戻ってきたのだ。
僕は心の中で、目の前のオレンジ色に光る世界に言った。
「ただいま。」
・・・
僕たちは、その夜、僕の部屋で裸で抱き合って眠った。
セックスもせず、ただ、二人で裸で抱き合って眠った。
・・・
僕は、また砂の星の夢を見た。
その夢は、やはり「続いて」いた。
・・・
僕たちが、遠い惑星に来て20回目の新月の夜が過ぎたころ、彼女は病気になった。故郷の星からいくつもの医薬品を持ってきてはいたが、それらは役に立たなかった。
日々衰えてゆく彼女を励まし見守りながら、僕は調査を続け、この星の新月前夜になると遠い故郷の星へとメッセージを送り続けた。
ある日、僕たちは気付く。
故郷の星がついに滅んでしまったことに。
こんなに離れていても、共有している意思によってそれが分かることに僕たちは改めて気付いた。
その夜、彼女は、あの時と同じように僕の小指に人差し指を付け、「幸せというのとは違うけど、あなたといられて良かったと思う」と言った。
僕はこの前は言わなかった「僕もだよ」という言葉を言おうとした。
しかし、その時には、彼女はもう生きるのをやめていた。
新月前夜がやってきた。
でも、僕にはもうメッセージ送る理由がなくなっていた。
僕は彼女の亡骸の首元に掛かっている、銀色のカプセルを鍵を使って開き、中のリング状の安全スイッチを引き抜いた。
カプセルは緑色に明るく、僕の視界を奪うほどに明るく輝いた。
この輝きが終わるころには、僕と彼女は炭化して小さな塊となり、水分は蒸発して気体になり消え去るだろう。
この部屋の物もすべて原形をとどめないだろう。
すべて終わったのだ。
「もう行っていいんだよ。」
緑の光はそう言っているようだった。
・・・
目が覚めた。
僕は彼女を抱きしめて泣いていた。
彼女は、僕の方をじっと見て、同じように泣いていた。
「君にも見えたんだね。」
彼女は何も言わずに僕と彼女の間にあるペンダントのトップをそうっと手のひらで包み、彼女の頬に当てた。そして、そのまま僕の方に頬を近づけた。
・・・
それから、僕たちは僕の部屋で暮らし始めた。
僕もNDAに署名して彼女の身元引受人になった。
僕たちは、新月前夜になると、ベランダに出て、マグカップのコーヒーを分けあいながら、骨のように白くて細くなった三日月を眺めた。
そうして、僕たちは、何も言わず、あの「緑の明かり」の部屋のことを想った。
僕たちは君たちのことを覚えているよ。
これからもずっと覚えている。
三日月が新月になる前の夜、君たちがずっと故郷の星に向けてメッセージを送り続けていたこと。
僕たちはきっとずっと覚えている。
君たちは、間違いなくここにいた。
骨のように白くて細い三日月と一緒に。
(おわり)
【あとがき】
「新月前夜、窓、そして君の事。」を最後まで読んでいただいて、ありがとうございます。
とてもうれしいです。
僕がこの話で描きたかったことは、僕たちは、普段は気付くことのない奇跡の中で生きている、ということです。
それはごくごく普通のこと、たとえば、夕陽に光る鉄塔がとても綺麗だったこと、昔の友達からの手紙を部屋の隅で見つけたこと、そういったことかもしれない。
僕はこの話のインスピレーションをいろんな所から得ました。
ある人が撮った写真。僕の中に澱のように積もった記憶。アインシュタインの言葉。
そういうものに触れて、これまで空気中で形とならずにモヤモヤとしていた物語が、急に形を持ち始めました。僕がしたことは、単に「それ」を空気中から引っ張り出して文章という形にした、ということだけでした。
僕は奇跡を信じています。
僕が今、こうやって生きていて、こういう物語を書いて、その物語をこうやって読んでくれている人がいること自体奇跡だからです。
また、物語を書く機会があるかもしれません。
その時は、また、読んでもらえれば嬉しいです。
最後までありがとうございました。
「私たちの生き方には二通りしかない。
奇跡など全く起こらないかのように生きるか、
すべてが奇跡であるかのように生きるかである。」
アルバート・アインシュタイン
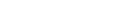 まで
まで